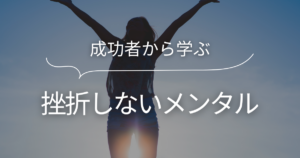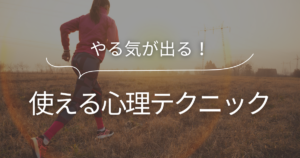モチベーションとは?なぜ継続が難しいのか?
トレーニングを始めたものの、「続かない」「やる気が出ない」と感じることは多いのではないでしょうか?モチベーションとは、行動を起こし続けるための原動力です。
モチベーションには、大きく分けて 「内発的動機づけ」 と 「外発的動機づけ」 の2種類があります。
内発的動機づけ
- 自分自身の興味や楽しさから生まれるモチベーション
- 例:「運動が楽しい」「達成感を味わいたい」「新しいことに挑戦したい」
外発的動機づけ
- 外部からの報酬や評価によって動機づけられるもの
- 例:「痩せたら周りから褒められる」「大会で優勝したい」「SNSで成果をシェアしたい」
継続するためには、この2つのモチベーションをうまく組み合わせることが重要です。
トレーニングのモチベーションを高める心理学的アプローチ
① 目標設定の科学「SMARTの法則」
目標が漠然としていると、モチベーションが下がります。そこで活用したいのが「SMARTの法則」です。
S:Specific(具体的) → 「週に3回ジムに行く」
M:Measurable(測定可能) → 「3ヶ月で体脂肪を2%減らす」
A:Achievable(達成可能) → 「1日30分の運動を続ける」
R:Relevant(関連性がある) → 「健康維持のために筋トレをする」
T:Time-bound(期限を決める) → 「6ヶ月後の大会に向けて準備する」
→ 具体的な目標を立てることで、達成に向けて行動しやすくなります。
② 習慣化の力「行動デザインの原則」
心理学者ジェームズ・クリアの著書『Atomic Habits』では、習慣化のコツとして 「行動を小さくすること」が紹介されています。
例:「運動を習慣化するための3つのステップ」
- トレーニングを小さく始める(1日5分のストレッチ)
- トリガーを設定する(朝起きたら腕立て伏せ1回)
- 報酬を用意する(運動後にお気に入りのプロテインを飲む)
→ 「やる気があるから行動する」のではなく、「行動するからやる気が出る」 という原則を活用しましょう!
③ 「ごほうび」をうまく使う(ドーパミンの活用)
脳は報酬を得るとドーパミンを分泌し、行動を強化します。
ごほうびの具体例
- トレーニング後にお気に入りのスムージーを飲む
- 1ヶ月続いたら、新しいトレーニングウェアを買う
- 友達とジムに行って、楽しくトレーニングする
→ 脳に「運動=楽しい」と学習させることで、継続しやすくなります!
④ 役割モデルを作る(社会的影響の活用)
「〇〇さんみたいになりたい!」と思える存在がいると、モチベーションが高まります。
- SNSで憧れの人をフォローする
- トレーニング仲間を作る
- 目標とするアスリートやモデルの習慣を真似する
→ 環境を整えることで、自然とやる気が高まる!
モチベーションを維持するためのテクニック
① 環境を整える
モチベーションは意志の力ではなく、環境によって大きく左右されます。
- 家の目につく場所にトレーニングウェアを置く
- ジムに通いやすいルートを探す
- フィットネスアプリを活用して記録する
② 「今日だけ頑張る」戦略
「毎日続けるのは大変」と思うと、やる気がなくなります。そこで 「今日だけは頑張ろう」 というマインドセットを持つのが効果的です。
- とりあえず5分だけ運動する
- 「やる気が出たらやる」ではなく「やればやる気が出る」
→ 始めることでモチベーションが湧いてくる!
おすすめの本5選(モチベーション向上に役立つ)
①『やり抜く力(GRIT)』アンジェラ・ダックワース
成功する人は才能ではなく「やり抜く力」がある。目標達成のための心理学を学べる1冊。
②『習慣が10割』吉井雅之
習慣を作ることがすべて。小さな行動を積み重ねることの重要性を解説。
③『スタンフォードのストレスを力に変える教科書』ケリー・マクゴニガル
ストレスは悪いものではなく、成長の糧になる。ストレスを味方につける方法を学べる本。
④『超習慣術』メンタリストDaiGo
意志の力に頼らずに継続するための具体的なテクニックを紹介。
⑤『Atomic Habits(複利で伸びる1つの習慣)』ジェームズ・クリア
世界的ベストセラー。小さな習慣を積み重ねることで、大きな成果を出す方法を解説。
まとめ|モチベーションを高めるための行動リスト
- 「SMARTの法則」を使って目標設定
- 小さな行動から始めて習慣化
- ごほうびを設定してドーパミンを活用
- SNSや仲間の影響を受ける環境を作る
- 「今日だけ頑張る」マインドセットを持つ
トレーニングのモチベーションは、心理学的アプローチを活用すれば継続しやすくなります!
無理なく楽しく続けるために、ぜひ実践してみてください!

-5.png)


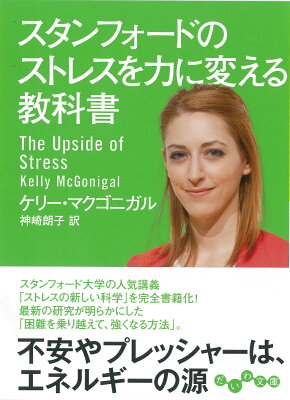

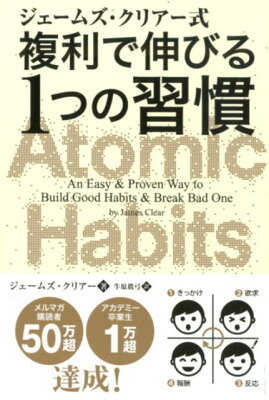
-5-300x158.png)
-17-300x158.png)
-2-300x158.png)
-75-300x158.png)
-71-300x158.png)
-5-300x158.png)